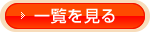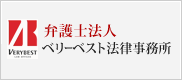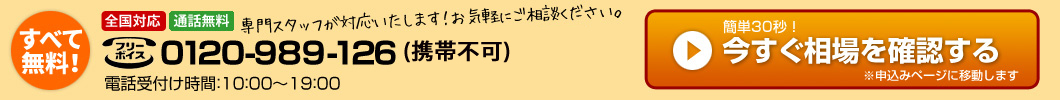鈴木良太【編集者・外壁塗装110番代表】
鈴木良太【編集者・外壁塗装110番代表】幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。
雨仕舞とは?重要性や防水との違い
雨仕舞と聞いて、どのような意味なのか詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。雨仕舞の役割は、雨水の滞留や浸入を防ぎ、排水がスムーズにできるようにすることです。
このページでは、雨仕舞とは何か?雨仕舞と防水の違いや、住宅で雨仕舞が施されている部分などについて説明いたします。雨漏りを防ぐうえで重要なポイントとなるため、必要性や構造を理解しておくことが大切です。
雨仕舞とは
雨仕舞(あまじまい)とは、建物内部に雨水が浸入しないようにする対策のことを言います。雨仕舞をしっかりと施すことで、雨が屋根やベランダなどに留まったり、建物内に入り込んだりせずに、正しく排水できるようになります。
もし雨仕舞が施されていないと、雨水が適切に排水できずに建物内部に浸入し、その結果雨漏りに発展してしまいます。雨漏りの発生を防ぎ、建物を守るためにも雨仕舞は非常に重要なポイントです。
防水と雨仕舞の違い
雨仕舞と同じように、防水の目的も雨水が建物内部に入り込まないようにすることです。しかし、厳密には次のような違いがあります。
防水とは、防水シートや防水性の高い塗料などを使用して、ベランダ床や屋根などの建材を守り、外部から建物内部に雨水が浸入しないようにすることです。
そして雨仕舞は、様々な種類・形の部材を取り付けて、建物に当たった雨が溜まらないようにしたり、雨水をスムーズに排水できるようにする仕組みのことを指します。
前述したように、雨水の浸入を防ぐという目的は同じですが、防水は「雨水から建物を守る」のが主な目的であるのに対し、雨仕舞は「雨水の浸入を防いだうえで、雨を下へ流す道を作る」といった役割も果たしています。
住宅に施されている主な雨仕舞
雨仕舞は建物あらゆる部分に施されています。雨仕舞が施工されている部分は、主に次のような箇所が挙げられます。
屋根の棟部分
 棟とは屋根の頂上部を指し、この部分には棟板金と呼ばれる金属製の部材が取り付けられています。屋根の棟部分は雨が当たりやすく、屋根材同士の継ぎ目でもあるので、雨水が浸入しやすい箇所です。
棟とは屋根の頂上部を指し、この部分には棟板金と呼ばれる金属製の部材が取り付けられています。屋根の棟部分は雨が当たりやすく、屋根材同士の継ぎ目でもあるので、雨水が浸入しやすい箇所です。
そのため、棟板金で覆って釘やビスでしっかりと固定し、棟板金と屋根材の間も隙間ができないようにコーキング材で埋めることが重要となります。
谷樋
 谷樋とは、屋根材同士の継ぎ目に生じる「谷」部分のことを指します。屋根に降った雨はこの谷樋に集まり、谷樋から雨樋に流れていく構造になっています。
谷樋とは、屋根材同士の継ぎ目に生じる「谷」部分のことを指します。屋根に降った雨はこの谷樋に集まり、谷樋から雨樋に流れていく構造になっています。
谷樋は雨が集中する箇所なので、雨漏りの原因箇所にもなりやすい部分です。そのため、谷部分にも板金を施工し、屋根内部に雨水が浸入するのを防ぎ、さらに雨水を溜めずに適切に排水できるようにする必要があります。
屋根の軒先・ケラバ
 まず軒先とは、雨樋が付いているほうの屋根の先端部分を指し、ケラバは雨樋が付いていないほうの先端部分のことを言います。
まず軒先とは、雨樋が付いているほうの屋根の先端部分を指し、ケラバは雨樋が付いていないほうの先端部分のことを言います。
軒先とケラバも雨が集まりやすい箇所なので、板金で覆って雨水の浸入を防ぎ、雨水が正しく排水されるようにすることが大切です。
外壁と屋根の取り合い部分
 取り合いとは、異なる建材が向かい合う接合部分のことを指します。
取り合いとは、異なる建材が向かい合う接合部分のことを指します。
外壁と屋根の取り合い部分は構造上、どうしても隙間が生じてしまうため、雨水が内部に入り込まないように板金やコーキング材を施工して、取り合い部分を保護する必要があります。
窓サッシ周り
 窓のサッシと外壁の間にはコーキング材が充填されており、このコーキング材の働きによって雨水が内部に浸入するのを防ぐことができます。また、サッシの内側には防水性を高めるために防水シートも施工されています。
窓のサッシと外壁の間にはコーキング材が充填されており、このコーキング材の働きによって雨水が内部に浸入するのを防ぐことができます。また、サッシの内側には防水性を高めるために防水シートも施工されています。
また、天窓の場合も同じような構造になっており、コーキング材や防水シートを施工して、室内に雨水が入り込まないようにします。
ベランダの立ち上がり
 立ち上がりとは、ベランダの床から延びている外壁部分のことを言います。ベランダ床と外壁の継ぎ目から雨水が入り込む恐れがあるため、浸水を防ぐために板金で覆ったり、コーキング材を充填して隙間を埋めます。
立ち上がりとは、ベランダの床から延びている外壁部分のことを言います。ベランダ床と外壁の継ぎ目から雨水が入り込む恐れがあるため、浸水を防ぐために板金で覆ったり、コーキング材を充填して隙間を埋めます。
ベランダの防水工事も重要ですが、雨仕舞がしっかりと施されていないと、外壁から雨水が染み込んでいってしまうので注意しなければなりません。
仕舞が機能しなくなる原因
経年劣化
雨仕舞の施工に用いられる板金やコーキング材、防水シートなどは年月の経過とともに劣化していきます。
劣化が進むと、剥がれやひび割れなどが発生して雨仕舞としての機能を果たせなくなり、やがて雨水が建物内部に浸入したり、雨水の流れに問題が生じて正しく排水されないといったトラブルが起きてしまいます。
施工不良
施工不良によって雨仕舞が機能しない場合もあります。施工不良のパターンは様々ですが、例として次のようなことが挙げられます。
・防水シートの貼り方に問題があった
・排水に必要な隙間までコーキング材で埋めてしまった
・板金がきちんと固定されていなかった
屋根や外壁内部には防水シートが施工されており、この防水シートを貼る順番にミスが生じるケースがあります。雨は上から下へ流れていくため、防水シート同士の継ぎ目から雨が入らないように、防水シートは下から上に貼っていく必要があります。
しかし、知識や経験が不足している業者だと、防水シートを上から下へ順に貼るといった間違いを犯し、その結果上から流れてきた雨が防水シート同士の継ぎ目に浸入してしまうのです。
自然災害
台風や強風などが原因で、板金の剥がれや浮きなどが生じるケースもあります。また、風で飛ばされてきた飛来物によって、部材が破損してしまう可能性も考えられます。
築年数が経っていない場合でも、台風や強風が起きた後は点検を行い、異常がみられる際は早めに専門業者に相談するようにしましょう。
まとめ
雨仕舞とは、板金やコーキング材などを使用して、建物の防水性を高める工事のことです。雨水を浸入させない、留まらせない、排水のための経路を保持するといった重要な役割を持ちます。
雨仕舞が機能していないと、建物内部に雨水が入り込んでしまい、雨漏りが発生します。雨漏りはシロアリの発生や、建物の耐震性の低下などの大きなトラブル繋がるため非常に危険です。
雨漏りが起こらないようにするためにも、信頼できる優良な業者に施工を依頼して、雨仕舞をしっかりと施してもらうことが大切です。
その他、雨漏り補修に関するお役立ちコンテンツ

外壁からの雨漏りであれば、コーキングによる応急処置が行えます。あくまでも応急処置なので、専門業者による調査・修理は必要です。ここでは、コーキングを施工するときの流れや注意点などについて説明したします。

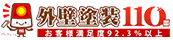



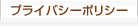


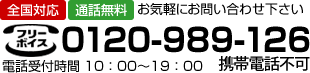


















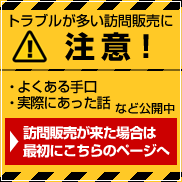

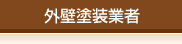
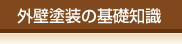
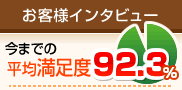
 S 様
S 様 Y 様
Y 様 M 様
M 様 M 様
M 様 S 様
S 様 N 様
N 様 S 様
S 様 M 様
M 様